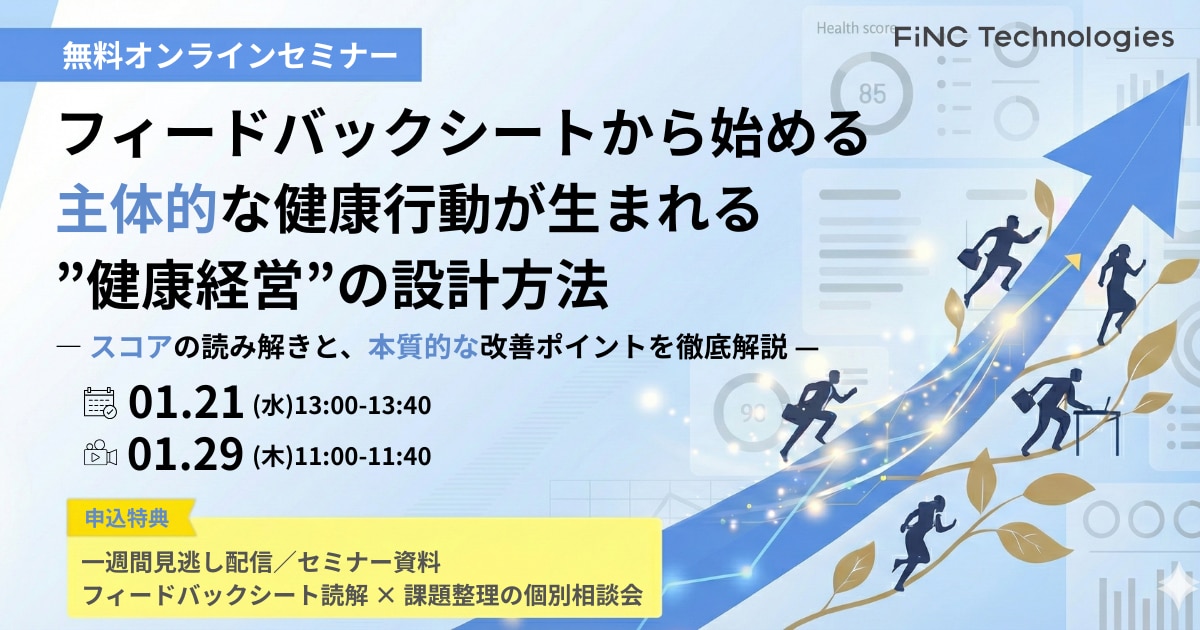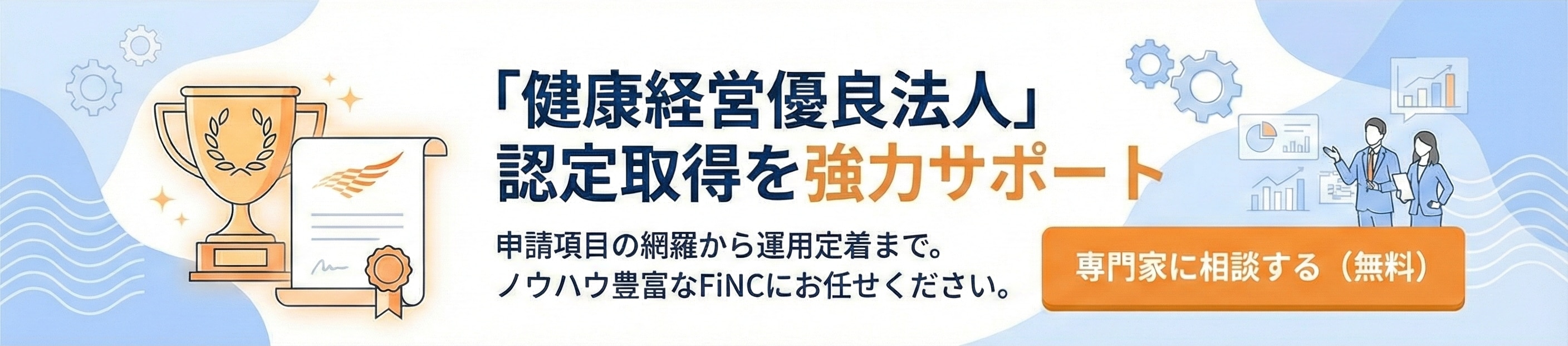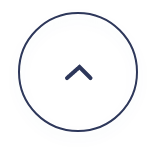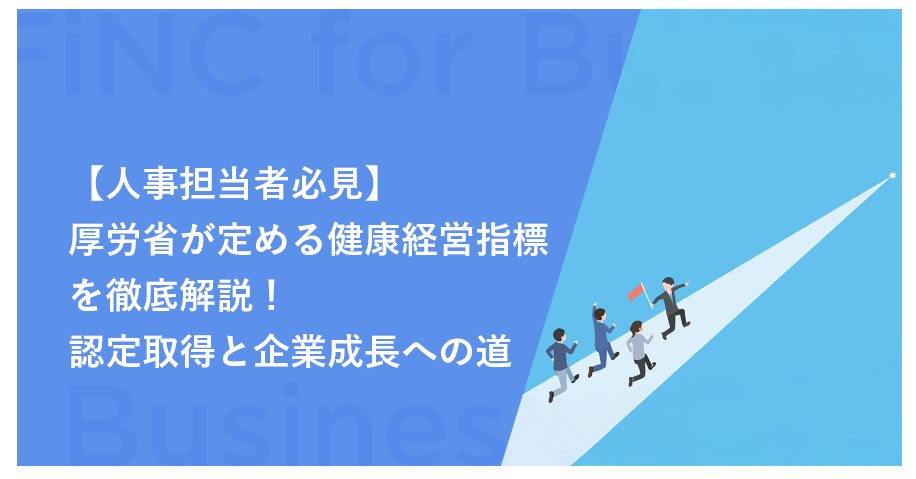
【人事担当者必見】厚労省が定める健康経営指標を徹底解説!認定取得と企業成長への道
この記事でわかること
- 健康経営指標の基本的な考え方
- 大規模法人向けの主要な指標項目とその解説
- 指標を活用した自社の健康経営の自己診断方法
- 健康経営をさらに改善するための具体的なアプローチ
- 健康経営を推進する上での注意点と成功事例
はじめに:健康経営は「投資」!人事担当者が知るべき厚労省指標の重要性

「健康経営」って言葉、最近よく耳にするけど、具体的に何をすればいいの?うちの会社も健康経営に取り組んでいるけど、今のシステムで本当に大丈夫かな?なんて、日々頭を悩ませている人事担当者さんも多いのではないでしょうか。
実は、健康経営は単なる福利厚生じゃなくて、従業員さんの健康を「未来への投資」と捉える、とっても戦略的な経営手法なんです。従業員さんがイキイキと働ける環境を整えることで、会社の生産性が上がったり、優秀な人材が集まってきたり、さらには企業イメージもグッとアップする、まさに一石二鳥どころか三鳥にもなる取り組みなんですよ。
特に、健康経営優良法人の認定を目指す大企業の人事担当者さんにとって、厚生労働省が定める「健康経営指標」を理解することは、まさに羅針盤を手に入れるようなもの。この指標をしっかり把握することで、自社の健康経営が今どのレベルにあるのか、どこを改善すればもっと良くなるのかが明確になります。
「今のシステムに課題を感じている…」そんなあなたもご安心ください!この記事では、厚労省が定める健康経営指標について、基本から大規模法人向けの具体的な評価項目、そしてその活用方法まで、カジュアルでフレンドリーな口調で徹底的に解説していきます。この記事を読み終える頃には、きっとあなたの会社の健康経営を次のステージに進めるヒントが見つかるはずです。さあ、一緒に健康経営の奥深さを探求していきましょう!
目次[非表示]
- 1.健康経営指標ってなんだろう?基本からわかりやすく解説!
- 2.大規模法人向け!主要な健康経営指標項目をチェックしよう
- 2.1.経営理念・方針:健康経営はトップからのメッセージがカギ!
- 2.2.組織体制:健康経営を支える強力なチームづくり
- 2.3.制度・施策実行:従業員の健康をサポートする具体的な取り組み
- 2.3.1.健康課題の把握と対策
- 2.3.2.健康経営の実践に向けた土台づくり
- 2.3.3.ワークライフバランス、仕事と治療の両立支援
- 2.3.4.具体的な健康保持・増進施策
- 2.4.評価・改善:PDCAサイクルで健康経営をブラッシュアップ!
- 2.5.法令遵守・リスクマネジメント:健康経営の土台はコンプライアンス
- 3.自社の健康経営、今どこにいる?指標を活用した自己診断のススメ
- 4.指標を改善につなげる!効果的な健康経営推進のポイント
- 5.健康経営を成功させる秘訣:事例から学ぶ実践のヒント
- 6.まとめ:健康経営指標を羅針盤に、持続可能な企業へ!
健康経営指標ってなんだろう?基本からわかりやすく解説!
さて、健康経営の重要性はわかったけど、「健康経営指標」って具体的に何を指すの?と疑問に思っている方もいるかもしれませんね。簡単に言うと、健康経営指標とは、企業が健康経営をどれくらい実践できているか、その取り組み状況や成果を測るための「ものさし」のようなものです。
この指標は、主に経済産業省と厚生労働省が連携して推進している「健康経営優良法人認定制度」と深く関わっています。健康経営優良法人に認定されるためには、毎年実施される「健康経営度調査」に回答し、そこで示される評価項目をクリアしていく必要があるんです。この評価項目こそが、私たちが「健康経営指標」と呼ぶものの実体に近いと言えるでしょう。
厚生労働省は、企業が従業員の健康保持・増進に取り組む上での基本的な考え方や、具体的な施策の方向性を示すガイドラインを策定しています。これらのガイドラインは、健康経営の「なぜ」と「何をすべきか」の基礎を提供してくれます。
一方、経済産業省は、より実践的な視点から「健康経営優良法人認定制度」を運営し、企業が健康経営に取り組む際の具体的な評価基準を設けています。この評価基準は、企業が健康経営を戦略的に推進するためのフレームワークとして機能し、健康経営度調査を通じて企業の取り組みを多角的に評価します。
つまり、健康経営指標とは、厚生労働省が示す基本的な考え方や方向性を踏まえつつ、経済産業省が設定する具体的な評価項目を通じて、企業の健康経営の「現在地」を把握し、さらに「次の一歩」を考えるための重要なツールなんです。ちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、これらの指標を理解し、活用することで、あなたの会社の健康経営はもっと明確な目標を持って進んでいけるようになりますよ!
大規模法人向け!主要な健康経営指標項目をチェックしよう
さあ、いよいよ本題です!あなたの会社が健康経営優良法人(大規模法人部門)の認定を目指すなら、どんな項目が評価されるのか、具体的に見ていきましょう。健康経営度調査の評価項目は、大きく分けて以下の5つの大項目で構成されています。これらを一つずつチェックしていくことで、自社の健康経営の強みと課題が見えてきますよ。
経営理念・方針:健康経営はトップからのメッセージがカギ!
健康経営は、経営層の強いコミットメントがあってこそ成功します。この項目では、経営者自身が健康経営の重要性を理解し、それを社内外に発信しているかが問われます。
- 健康宣言の社内外への発信:アニュアルレポートや統合報告書などで、健康経営への取り組みを積極的に開示しているか。
- 従業員パフォーマンス指標及び測定方法の開示:健康経営が従業員のパフォーマンスにどう影響しているかを測り、その結果を開示しているか。
- トップランナーとしての健康経営の普及:自社だけでなく、社会全体に健康経営の重要性を広める活動をしているか。
経営層が「従業員の健康は会社の財産だ!」と本気で考えているメッセージは、従業員さんのモチベーションにも直結しますよね。
組織体制:健康経営を支える強力なチームづくり
健康経営を推進するには、それを実行する組織体制が不可欠です。誰が責任を持ち、どのように進めていくのかが評価されます。
- 健康づくり責任者が役員以上:健康経営の責任者が経営層にいることで、意思決定がスムーズになります。
- 健康経営推進に関する経営レベルの会議での議題・頻度:定期的に経営会議で健康経営が議論されているか。
- 産業医・保健師の関与:専門家である産業医や保健師が、健康経営の計画・実行・評価に深く関わっているか。
- 健保組合等保険者との連携:健康保険組合などと連携し、より効果的な健康増進策を検討・実施しているか。
専門家の知見を借りたり、健保組合と協力したりすることで、より質の高い健康経営が実現できます。
制度・施策実行:従業員の健康をサポートする具体的な取り組み
ここが一番イメージしやすいかもしれませんね。実際に従業員さんの健康を守り、増進するための具体的な制度や施策が評価されます。多岐にわたるので、一つずつ確認していきましょう。
健康課題の把握と対策
まずは、従業員さんの健康状態を正確に把握し、それに基づいた対策を立てることが重要です。
- 健康経営の具体的な推進計画:健康課題を明確にし、それに対する具体的な目標と計画があるか。
- 定期健診受診率(実質100%):定期健康診断を従業員全員が受けているか、そしてその受診率が実質100%であるか。
- 受診勧奨の取り組み:健康診断で異常が見つかった従業員に対し、医療機関への受診を促す取り組みをしているか。
- ストレスチェックの実施:ストレスチェックを適切に実施し、その結果を分析・活用しているか。
健康経営の実践に向けた土台づくり
従業員さん一人ひとりが健康について考え、行動できるような環境を整えることも大切です。
- ヘルスリテラシーの向上:健康に関する正しい知識を従業員さんに提供し、自ら健康管理ができるよう支援しているか。
- 管理職又は従業員に対する教育機会の設定:健康経営に関する研修やセミナーなどを実施しているか。
ワークライフバランス、仕事と治療の両立支援
働き方そのものが健康に大きく影響します。働きやすい環境づくりも健康経営の一環です。
- コミュニケ-ションの促進に向けた取り組み:従業員同士のコミュニケーションを活性化させる施策があるか。
- 私病等に関する復職・両立支援の取り組み:病気で休職した従業員がスムーズに復職できるよう、また治療と仕事を両立できるよう支援しているか。
具体的な健康保持・増進施策
日々の生活習慣や健康課題に合わせた、具体的なサポートが求められます。
- 保健指導の実施及び特定保健指導実施機会の提供:生活習慣病予防のための保健指導や特定保健指導を実施しているか。
- 食生活の改善に向けた取り組み:健康的な食生活をサポートする食堂メニューや情報提供などがあるか。
- 運動機会の増進に向けた取り組み:運動習慣を身につけるためのイベントや施設利用補助などがあるか。
- 女性の健康保持・増進に向けた取り組み:女性特有の健康課題に配慮した施策があるか。
- 長時間労働者への対応に関する取り組み:長時間労働による健康リスクを軽減するための対策があるか。
- メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み:メンタルヘルス不調の早期発見・早期対応、相談体制の整備などがあるか。
- 感染症予防に関する取組:インフルエンザ予防接種の補助や感染症対策の啓発などがあるか。
- 喫煙率低下に向けた取り組み・受動喫煙対策:禁煙サポートや分煙対策など、喫煙に関する取り組みがあるか。
これらの施策は、従業員さんの健康を守るだけでなく、会社へのエンゲージメントを高める上でも非常に重要です。自社に合った施策を積極的に取り入れていきましょう。
評価・改善:PDCAサイクルで健康経営をブラッシュアップ!
健康経営は一度やったら終わりではありません。効果を測定し、改善を繰り返すことで、より良いものになっていきます。
- 健康経営の実施についての効果検証:実施した施策がどれくらいの効果があったのかを定期的に評価し、改善につなげているか。
従業員さんの健康データやアンケート結果などを活用して、施策の効果を「見える化」することが大切です。
法令遵守・リスクマネジメント:健康経営の土台はコンプライアンス
健康経営を進める上で、法令遵守は基本中の基本です。従業員さんの健康に関する法的な義務をきちんと果たしているかが問われます。
- 定期健診の実施、ストレスチェックの実施、労働基準法または労働安全衛生法に係る違反がないこと:これらは自主申告事項ですが、健康経営の信頼性を担保する上で非常に重要な項目です。
これらの5つの大項目とそれに付随する小項目をクリアしていくことが、健康経営優良法人認定への道となります。一つ一つの項目を丁寧に確認し、自社の取り組みを見直す良い機会にしてくださいね。
自社の健康経営、今どこにいる?指標を活用した自己診断のススメ
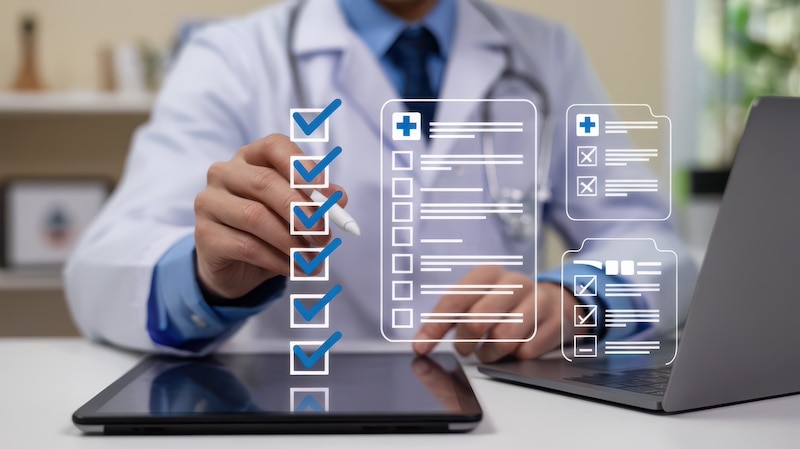
さて、ここまで大規模法人向けの健康経営指標の主要な項目を見てきました。たくさんの項目があって、ちょっと圧倒されちゃったかもしれませんね。でも大丈夫!これらの指標は、あなたの会社の健康経営の「現在地」を知るための、とっても便利なツールなんです。
チェックリストで現状を把握しよう!
先ほどご紹介した各項目を、まるでチェックリストのように活用してみてください。例えば、
- 「健康宣言は社内外に発信できているかな?」
- 「健康づくり責任者は役員以上かな?」
- 「定期健診の受診率は実質100%を達成できているかな?」
- 「ストレスチェックの結果は、ちゃんと分析して活用できているかな?」
といった具合に、一つ一つの項目に対して「できている」「一部できている」「まだできていない」といった形で、現状を正直に評価してみましょう。この自己診断を通じて、自社の健康経営の「強み」と「弱み」が浮き彫りになってくるはずです。
「システムに課題を感じている」あなたへ
もしあなたが「今の健康経営システムに課題を感じている」のであれば、この指標は既存システムの評価軸としても大いに役立ちます。例えば、
- データ連携の課題:健康診断データやストレスチェックの結果が、バラバラのシステムに散らばっていて、効果検証に時間がかかっていませんか?
- 施策実行の課題:従業員への健康情報提供や保健指導が、手作業が多くて非効率になっていませんか?
- 効果測定の課題:実施した施策の効果が、具体的な数値として見えにくく、改善につなげにくいと感じていませんか?
これらの課題は、健康経営指標の「評価・改善」や「制度・施策実行」の項目と密接に関わっています。自己診断の結果、もし既存システムがこれらの指標達成の足かせになっているようであれば、新しいシステムの導入を検討する良いタイミングかもしれませんね。
自己診断で見つかった「できていないこと」の次の一歩
自己診断で「まだできていないこと」が見つかっても、落ち込む必要はありません。むしろ、それはあなたの会社がさらに成長するための「伸びしろ」です!大切なのは、その「できていないこと」を具体的にどう改善していくか、次のステップを考えることです。
例えば、「従業員のヘルスリテラシー向上」が課題であれば、健康に関する情報提供の方法を見直したり、専門家を招いたセミナーを企画したりするのも良いでしょう。「メンタルヘルス不調者への対応」が不十分であれば、相談窓口の設置やラインケア研修の導入を検討するべきです。
この自己診断は、健康経営を「なんとなく」進めるのではなく、明確な目標を持って「戦略的に」推進するための第一歩となります。ぜひ、時間を取ってじっくりと取り組んでみてください。
指標を改善につなげる!効果的な健康経営推進のポイント

自己診断で自社の健康経営の現状が把握できたら、次はいよいよ改善フェーズです!せっかく見つけた課題も、具体的な行動につながらなければもったいないですよね。ここでは、健康経営指標を改善につなげるための効果的なポイントをいくつかご紹介します。
データに基づいた施策立案で「見える化」を徹底!
「なんとなく良さそうだから」で施策を決めていませんか?健康経営を効果的に推進するには、データに基づいた客観的な判断が不可欠です。例えば、
- 健康診断結果の活用:従業員さんの健康診断結果を分析し、生活習慣病のリスクが高い層や、特定の健康課題を抱える層を特定しましょう。その上で、対象者に合わせた保健指導や特定保健指導を強化するなどの対策を講じます。
- ストレスチェック結果の活用:ストレスチェックの結果から、高ストレス者への面接指導を促すだけでなく、部署ごとのストレス状況や職場環境の課題を把握し、組織的な改善策を検討しましょう。例えば、コミュニケーション不足が原因であれば、社内イベントの企画や1on1ミーティングの推奨などが考えられます。
- 従業員アンケートの実施:従業員さんの健康意識やニーズ、現在の健康施策への満足度などを定期的にアンケートで把握することも重要です。従業員さんの「生の声」は、施策改善の貴重なヒントになります。
これらのデータを「見える化」することで、施策の効果を客観的に評価し、PDCAサイクルを回しながら継続的に改善していくことができます。データは健康経営の羅針盤となる、大切な情報源ですよ。
従業員のエンゲージメントを高めるための工夫
どんなに素晴らしい施策も、従業員さんが積極的に参加してくれなければ意味がありません。従業員さんの「自分ごと」として健康経営に取り組んでもらうための工夫が必要です。
- インセンティブの導入:健康イベントへの参加や、健康目標達成者へのインセンティブ(例:健康ポイント、景品など)を設けることで、参加意欲を高めることができます。
- 楽しさの追求:ウォーキングイベントや健康レシピコンテストなど、楽しみながら健康増進に取り組めるような企画を導入しましょう。ゲーム感覚で参加できるアプリの活用も有効です。
- トップからのメッセージ:経営層や管理職が率先して健康増進に取り組む姿勢を見せることで、従業員さんの意識も変わってきます。健康経営は「会社全体で取り組むもの」という意識を醸成しましょう。
外部サービスや専門家の活用で効率アップ!
「自社だけで全てをやるのは大変…」と感じることもあるかもしれません。そんな時は、外部の専門家やサービスを上手に活用するのも賢い選択です。
- 健康経営コンサルティング:健康経営の専門家から、自社の状況に合わせたアドバイスやサポートを受けることで、より効果的かつ効率的に健康経営を推進できます。
- 健康管理システム:健康診断結果やストレスチェック結果の一元管理、従業員への健康情報配信、オンライン保健指導など、多岐にわたる機能を備えたシステムを導入することで、人事担当者さんの業務負担を軽減し、より戦略的な健康経営が可能になります。
特に、従業員数1000名以上の大企業では、多岐にわたる従業員の健康データを効率的に管理し、個々に合わせたサポートを提供できるシステムの導入が、健康経営を成功させる鍵となります。今のシステムに課題を感じているなら、ぜひ一度、最新の健康管理システムを検討してみてはいかがでしょうか。
健康経営を成功させる秘訣:事例から学ぶ実践のヒント
健康経営指標を理解し、自社の課題を把握し、改善策を検討する。ここまでのステップを踏んだら、次は具体的な成功事例からヒントを得て、自社の健康経営をさらに加速させましょう。ここでは、健康経営を実践し、成果を出している企業の事例(架空の事例、または一般論としての成功パターン)をご紹介します。
事例1:従業員の健康意識向上に成功したA社の取り組み
従業員数1500名の大手製造業A社では、以前から健康診断の受診率は高かったものの、生活習慣病予備群の割合が高いという課題を抱えていました。そこでA社は、健康経営指標の「制度・施策実行」における「食生活の改善に向けた取り組み」と「運動機会の増進に向けた取り組み」に注目。
まず、社内食堂のメニューを栄養バランスの取れたものに刷新し、カロリー表示を義務化。さらに、管理栄養士による個別相談会を定期的に開催しました。運動面では、社内にフィットネススペースを設置し、専門トレーナーによる指導を受けられる環境を整備。また、部署対抗のウォーキングイベントを定期的に開催し、健康アプリと連携して歩数を競い合うことで、従業員の運動習慣化を促進しました。
これらの取り組みの結果、1年後には生活習慣病予備群の割合が5%減少し、従業員アンケートでは「健康意識が高まった」という回答が80%に達しました。従業員の健康意識向上は、生産性の向上や医療費の抑制にもつながり、A社の企業価値向上に大きく貢献しています。
事例2:メンタルヘルス対策で離職率を改善したB社の事例
従業員数1200名のIT企業B社では、急速な事業拡大に伴い、従業員のメンタルヘルス不調による休職者や離職者が増加傾向にありました。B社は健康経営指標の「制度・施策実行」における「メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み」を強化することを決定。
まず、ストレスチェックの結果を詳細に分析し、高ストレス者への医師面接指導を徹底。さらに、社内外に相談窓口を複数設置し、匿名で利用できるカウンセリングサービスを導入しました。管理職向けには、部下のメンタルヘルス不調に早期に気づき、適切に対応するためのラインケア研修を義務化。また、従業員が気軽にリフレッシュできる休憩スペースを増設し、定期的にマインドフルネス研修を実施するなど、予防的なアプローチも強化しました。
これらの取り組みにより、B社ではメンタルヘルス不調による休職者数が半減し、離職率も前年比で3%改善しました。従業員からは「会社がメンタルヘルスを重視してくれていると感じる」という声が多く聞かれ、従業員満足度の向上にもつながっています。B社は、メンタルヘルス対策を強化することで、従業員が安心して長く働ける環境を築き、企業の持続的な成長を実現しています。
これらの事例は、健康経営指標を単なるチェック項目として捉えるのではなく、自社の課題解決のための「羅針盤」として活用することで、具体的な成果につながることを示しています。ぜひ、自社の状況に合わせて、これらのヒントを参考にしてみてくださいね。
まとめ:健康経営指標を羅針盤に、持続可能な企業へ!
皆さん、お疲れ様でした!この記事では、健康経営を成功に導くための羅針盤となる「健康経営指標」について、基本から具体的な活用法までを徹底解説しました。
この記事のポイント
- 健康経営は未来への投資:従業員の健康は、生産性や企業イメージ向上に直結する重要な経営戦略です。
- 指標は5つの柱で構成:①経営理念・方針、②組織体制、③制度・施策実行、④評価・改善、⑤法令遵守が評価の軸となります。
- 自己診断から始めよう:指標をチェックリストとして活用し、自社の「強み」と「弱み」を客観的に把握することが、改善の第一歩です。
- データ活用がカギ:健康診断やストレスチェックの結果を分析し、データに基づいた効果的な施策を立て、PDCAサイクルを回しましょう。
「今のシステムに課題を感じている…」そんな人事担当者さんこそ、この健康経営指標を新たな視点として活用するチャンスです。指標を基に自社の取り組みを見直し、従業員一人ひとりが輝く、持続可能な企業を一緒に目指していきましょう!
もし、具体的な施策の導入やシステムの検討でお困りでしたら、いつでもお気軽にご相談ください。あなたの会社の健康経営を、私たちも全力でサポートさせていただきます!
✅ FiNC for BUSINESS のサービス資料はこちら
📢 無料相談・お問い合わせはこちら