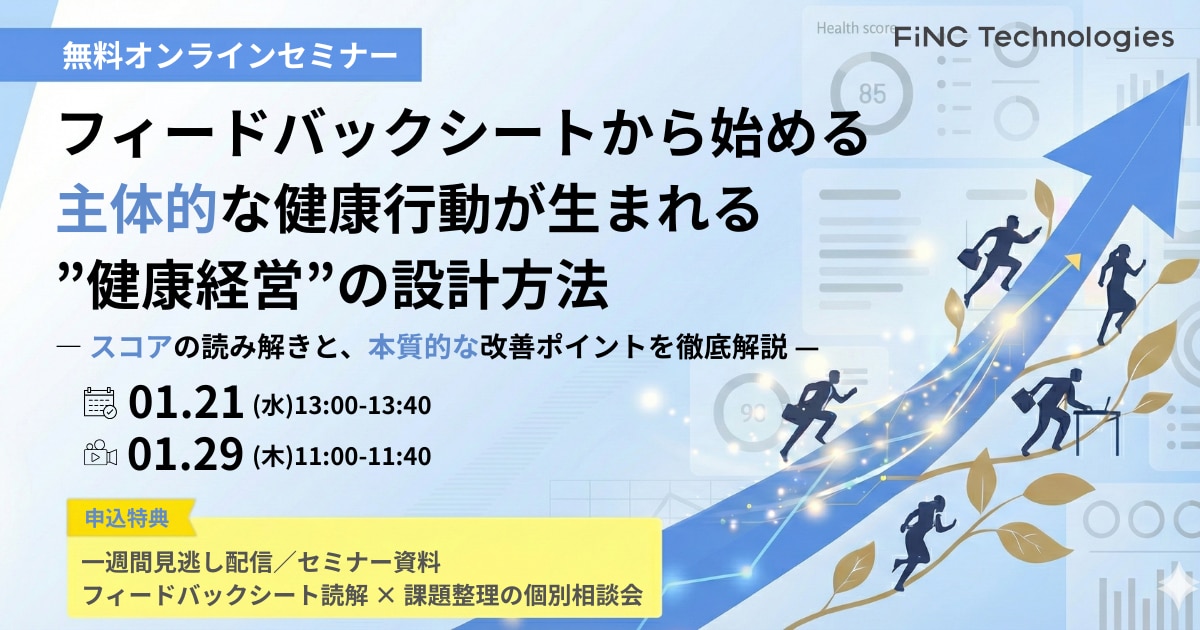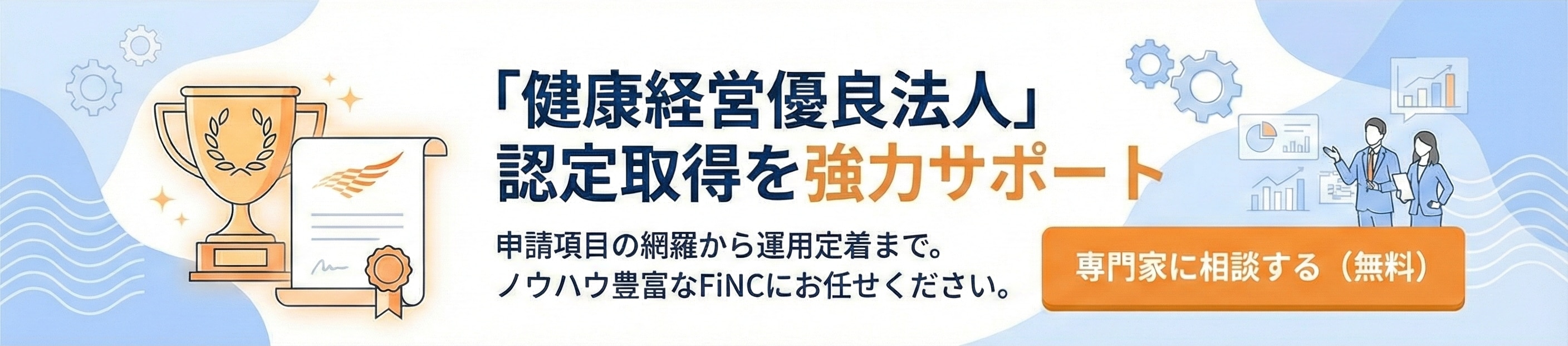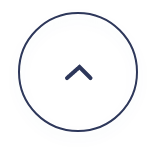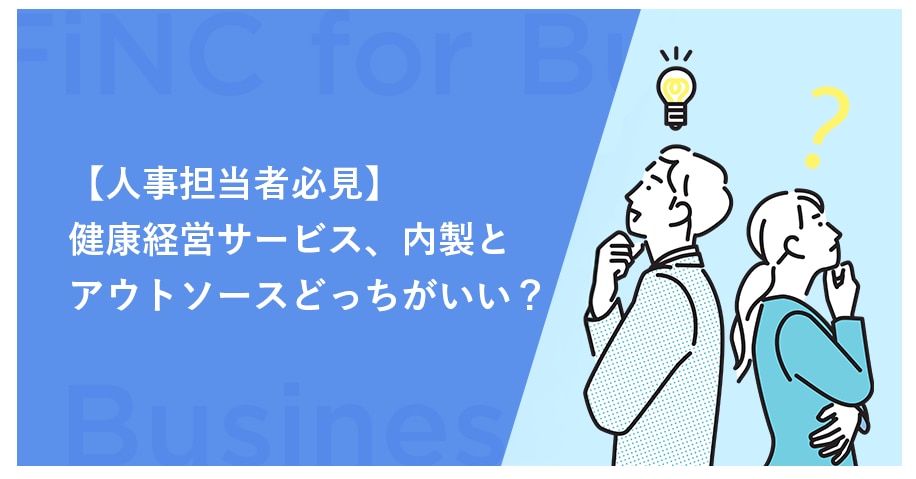
【人事担当者必見】健康経営サービス、内製とアウトソースどっちがいい?徹底比較でわかる自社に合う選び方

「健康経営優良法人の認定は受けたものの、思うように成果が上がらない…」
「今のやり方で、本当に従業員の健康と会社の成長につながっているんだろうか?」
こんにちは!企業の健康経営をサポートするメディアの編集長です。
最近、従業員1,000名以上の大企業の人事担当者の方から、こんなお悩みをよく伺います。
健康経営の重要性は理解しているし、すでに何らかのシステムやツールは導入している。でも、「運用が形骸化している」「担当者の負担が大きい」「効果が見えにくい」といった課題を感じ、新しいシステムの導入を検討されている方が多いようです。
そこで今回は、健康経営の推進方法を「内製」と「アウトソース(外部サービス利用)」に分け、それぞれのメリット・デメリットを徹底比較!すでに取り組んでいる企業だからこそ見えてくる課題に寄り添いながら、自社に本当に合うサービスの選び方を、分かりやすく解説していきます。
この記事でわかること
- 健康経営の推進体制におけるよくある課題
- 内製で進める場合のメリット・デメリット
- 外部サービスを利用するメリット・デメリット
- 代表的なサービスタイプの比較
- 自社にピッタリなサービスの選び方
健康経営の推進体制における課題
健康経営を推進する中で、多くの企業が以下のような課題に直面しています。
- 担当者の負担増: 人事や総務の担当者が通常業務と兼務しているケースが多く、業務負荷が高くなりがちです。 これにより、施策が中途半端になったり、継続が難しくなったりします。
- ノウハウ不足: 健康経営は、健康管理、メンタルヘルス、労働法規など幅広い専門知識が求められます。 社内だけで質の高い施策を企画・実行するのは簡単ではありません。
- 従業員の関心が低い: 経営層や担当者が意欲的でも、従業員一人ひとりの健康への意識が低いと、せっかくの制度やイベントも利用されず、形骸化してしまいます。
- 効果測定の難しさ: 施策の成果が生産性向上や業績にどう結びついているのか、効果を数値で示しにくいという課題があります。
これらの課題を解決する手段として、「内製」の強化、あるいは「アウトソース」の活用が検討されるわけです。
内製で進める場合のメリット・デメリット

まずは、自社のリソースで健康経営を推進する「内製」のメリットとデメリットを見ていきましょう。
メリット
- ノウハウの蓄積: 自社で試行錯誤を繰り返すことで、従業員の健康課題や効果的なアプローチに関する独自のノウハウが社内に蓄積されます。 これは将来的に企業の大きな財産になります。
- 柔軟な対応: 社内の状況に合わせて、施策の企画や改善をスピーディーかつ柔軟に行うことができます。
- 企業文化との連携: 自社の経営理念やビジョンと健康経営を強く結びつけ、企業文化として浸透させやすいです。
デメリット
- 担当者の負担が大きい: 企画、実行、効果測定まで全てを担うため、担当部署や担当者の負担が非常に大きくなります。
- 専門性の限界: メンタルヘルス対策や保健指導など、専門的な知見が必要な領域では、対応に限界があります。
- コスト管理が複雑化: 人件費や設備投資などが他の経費と混在し、健康経営にかかる正確なコストを把握しにくくなる可能性があります。
- 視野が狭くなる可能性: 社内の視点に偏ってしまい、客観的な評価や新しいアイデアが生まれにくい場合があります。
「まさに、うちの課題だ…」と感じた方も多いのではないでしょうか?
もし、担当者の負担増や専門知識不足でお悩みなら、一度外部の専門家の力を借りることも検討してみませんか?
外部サービス利用の利点・リスク
次に、健康経営支援サービスなどを利用する「アウトソース」の利点とリスクを見ていきましょう。
メリット
- 業務負担の軽減: 健康診断の手配・管理、ストレスチェックの実施、データ分析といった煩雑な業務を委託することで、担当者の負担を大幅に軽減できます。
- 専門的なサポート: 産業医や保健師、カウンセラーといった専門家による質の高いサービスを受けることができます。 これにより、従業員も安心して利用できます。
- 豊富なプログラム: 運動、食事、メンタルヘルスなど、自社だけでは用意できない多様なプログラムやアプリを活用でき、従業員の参加を促進します。
- 客観的な効果測定: 第三者の視点で施策の効果を分析・評価してもらえるため、客観的なデータに基づいた改善が可能になります。
デメリット
- コストがかかる: 当然ながら、外部に委託するための費用が発生します。 サービス内容とコストが見合っているか、慎重な判断が必要です。
- ノウハウが蓄積されにくい: 業務を丸投げしてしまうと、自社に健康経営に関する知見が蓄積されにくい可能性があります。
- 情報漏洩のリスク: 従業員の個人情報である健康データを外部に渡すため、委託先のセキュリティ体制を厳しくチェックする必要があります。
- サービスのミスマッチ: 提供されるサービスが自社の課題や文化に合わない場合、思うような効果が得られないことがあります。
代表的サービス比較表
健康経営を支援する外部サービスには、様々な種類があります。ここでは代表的なタイプを比較表にまとめました。自社の課題はどのタイプで解決できそうか、考えてみましょう。
サービスタイプ | 主な内容 | こんな企業におすすめ |
|---|---|---|
健康管理システム | 健康診断結果、ストレスチェック、勤怠データなどを一元管理・分析。高リスク者の可視化など。 | ・紙やExcelでのデータ管理に限界を感じている ・複数拠点の健康情報をまとめて管理したい ・データに基づいた戦略を立てたい |
オンライン保健指導 | 産業医や保健師とのオンライン面談。特定保健指導のサポートなど。 | ・専門職の面談設定や調整に手間がかかっている ・地方拠点など、専門職が訪問しにくい環境がある |
ヘルスケアアプリ | 従業員がスマホで食事・運動・睡眠などを記録。健康増進イベントの実施など。 | ・従業員の健康への関心を高めたい ・楽しみながら健康習慣を身につけてほしい ・社内のコミュニケーションを活性化したい |
コンサルティング | 健康経営優良法人の認定取得支援、施策の企画立案、効果測定のサポートなど。 | ・何から手をつければ良いかわからない ・より戦略的に健康経営を推進したい ・客観的なアドバイスが欲しい |
福利厚生サービス | スポーツジムの割引利用、健康的な食事の提供(置き社食など)、各種相談窓口の設置など。 | ・従業員の満足度を向上させたい ・幅広いニーズに応える健康支援策を導入したい |
自社の課題に合うサービスは見つかりましたか?
FiNC for BUSINESSは、ヘルスケアアプリを軸に、健康管理システムの機能や専門家によるサポートまでをワンストップで提供しています。
自社に合うサービスの選び方
では、数あるサービスの中から、自社に最適なものを選ぶにはどうすればよいのでしょうか。絶対に押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。
ポイント1:自社の「健康課題」を明確にする
まずは、自社の健康課題を明確にすることが最も重要です。
「なんとなく良さそう」で選んでしまうと、ミスマッチが起こりがちです。
- 健康診断のデータ: 生活習慣病のリスクが高い層が多いのか?
- ストレスチェックの結果: 高ストレス者の割合や、その原因は何か?
- 従業員アンケート: 運動不足、睡眠不足、食生活の乱れなど、どんな悩みを抱えているか?
これらのデータを分析し、「メンタルヘルス対策を強化したい」「生活習慣病の予防に力を入れたい」といった具体的な課題を特定しましょう。
ポイント2:従業員が「使いたくなる」か?
どんなに優れたシステムでも、従業員に使ってもらえなければ意味がありません。特に、健康への関心が低い層をいかに巻き込むかが成功のカギです。
- 操作は簡単か?: スマホアプリなど、直感的で使いやすいインターフェースか?
- 参加したくなる工夫はあるか?: ポイント制度やチーム対抗戦など、ゲーム感覚で楽しめる要素はあるか?
- 個人のニーズに応えられるか?: 全員一律のプログラムだけでなく、個人の興味や課題に合わせて選べる選択肢はあるか?
導入前にデモ画面を触らせてもらうなどして、従業員目線で使いやすさをチェックすることが大切です。
ポイント3:導入後の「サポート体制」は万全か?
サービス導入はゴールではなく、スタートです。導入後にしっかりと伴走してくれるパートナーを選びましょう。
- 活用のための支援: 担当者向けの勉強会や、従業員への利用促進キャンペーンなどを手伝ってくれるか?
- 効果測定と改善提案: 定期的なレポートや分析を通じて、客観的な評価と次の打ち手を提案してくれるか?
- 専門家との連携: 必要に応じて、産業医や保健師、カウンセラーなどの専門家と連携できる体制があるか?
導入実績が豊富で、自社と似たような規模や業種の企業の支援経験があるかどうかも、重要な判断材料になります。

まとめ
健康経営の推進において、「内製」と「アウトソース」のどちらか一方が絶対的に正しいというわけではありません。
- 内製: 自社にノウハウを蓄積し、企業文化として根付かせたい場合に有効。ただし、担当者の負担と専門性の壁が課題。
- アウトソース: 専門家の力を借りて、効率的かつ質の高い施策を実行したい場合に有効。ただし、コストとサービスの見極めが重要。
大切なのは、自社の課題を正しく把握し、それを解決するために最適な手段を選ぶことです。
「内製でできる部分」と「外部の力を借りる部分」をうまく組み合わせるハイブリッド型も、有効な選択肢の一つです。
この記事が、貴社の健康経営を次のステージに進めるための一助となれば幸いです。
✅ FiNC for BUSINESS のサービス資料はこちら
📢 無料相談・お問い合わせはこちら