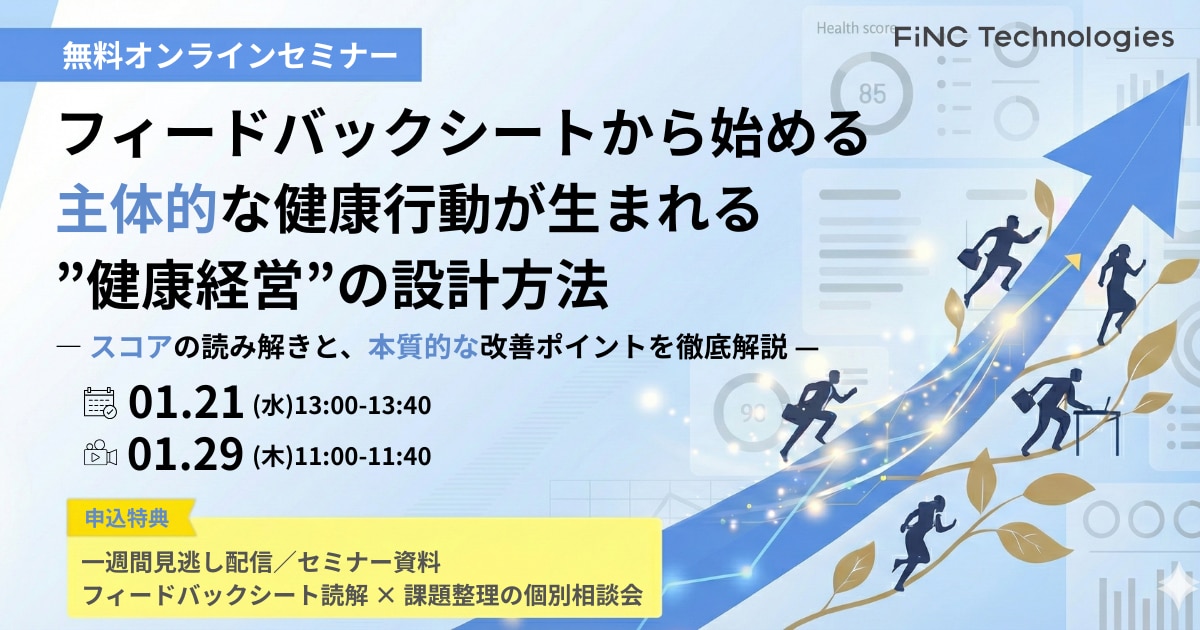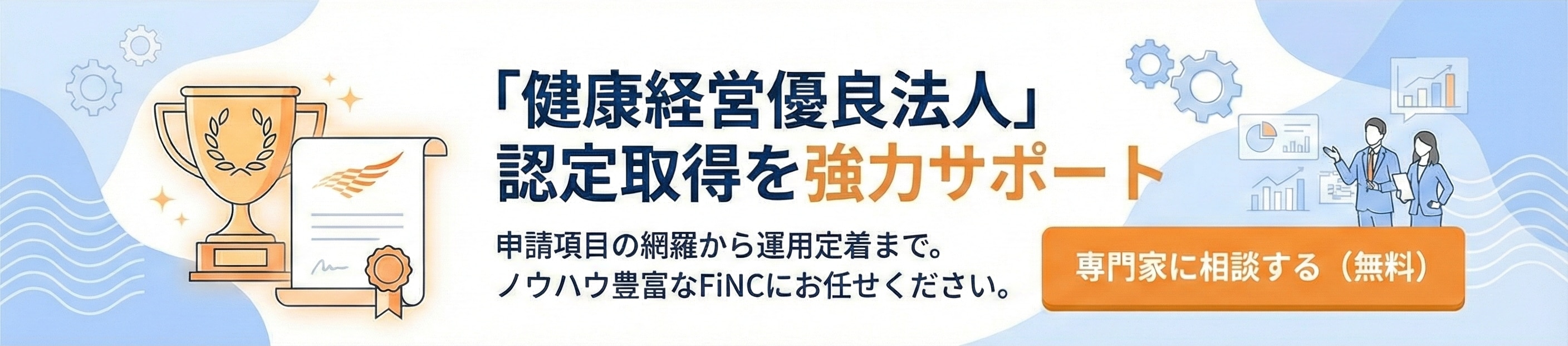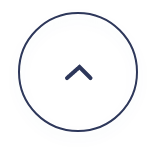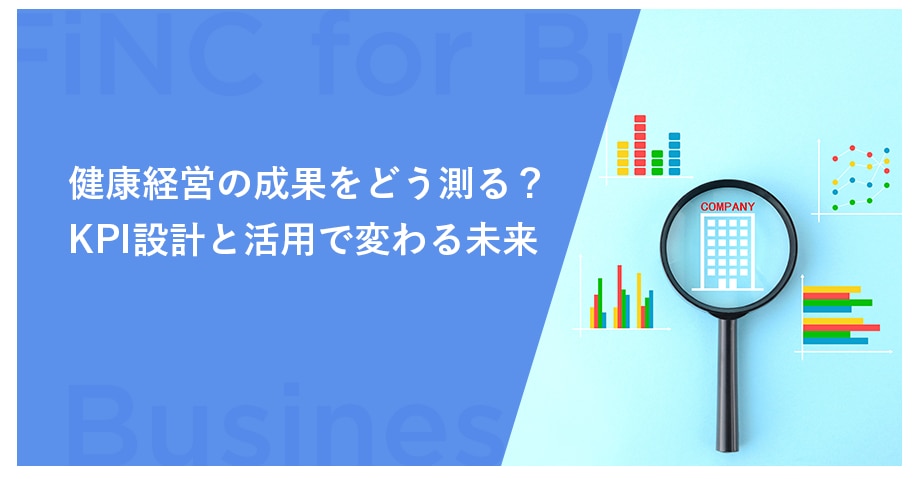
健康経営の成果をどう測る?KPI設計と活用で変わる未来
この記事でわかること
- 健康経営におけるKPI設計の重要性がわかる
- 健康経営でよく使われるKPIの具体例がわかる
- KPI設定の具体的な手順とデータ収集・可視化の方法がわかる
- KPIを活用した改善事例から、自社での取り組みのヒントが得られる

はじめに:健康経営、本当に「成果」出てますか?
「健康経営優良法人」の認定を目指して、健康経営システムやツールを導入したものの、
「あれ?本当に効果が出てるのかな?」
と、その成果が見えにくくて悩んでいませんか?従業員1000名以上の大企業の人担当者さんなら、きっと一度はそんな疑問を感じたことがあるはず。
従業員1000名以上の大企業の人事担当者さんなら、きっと一度はそんな疑問を感じたことがあるはず。
健康経営は、ただ施策を導入するだけではもったいない!
その効果を「見える化」して、経営戦略にしっかり組み込むことが、これからの健康経営には欠かせません。
そこで今回は、健康経営の成果を客観的に測るための「KPI設計」と、その「活用法」について、しっかり解説していきますね!
この記事を読めば、あなたの会社の健康経営が、もっとパワフルに、もっと効果的に進化するヒントが見つかるはず。
さあ、一緒に健康経営の「見える化」の秘訣を探っていきましょう!
健康経営の成果を「見える化」するKPI設計の重要性

健康経営って、従業員の健康をサポートするだけじゃないんです。実は、企業の生産性向上や業績アップにも大きく貢献する、とっても重要な経営戦略なんですよ。
でも、「具体的にどう貢献してるの?」って聞かれると、ちょっと困っちゃうこと、ありませんか?
そこで登場するのが「KPI(重要業績評価指標)」なんです!
KPIを設定するってことは、健康経営の取り組みが、従業員の健康状態の改善、ひいては企業の生産性や業績向上にどう繋がっているのかを、数字でハッキリと「見える化」すること。これによって、健康への投資がどれだけ価値を生み出しているかを客観的に評価できるようになるんです。
戦略マップで健康投資の道筋を明確に!
経済産業省も推奨しているのが「戦略マップ」の考え方。
これは、健康経営に「どんな資源を投入して(インプット)」、「どんな活動をして(アクティビティ)」、その結果「どんな成果が出て(アウトプット)」、最終的に「どんな結果に繋がったのか(アウトカム)」という一連の流れを体系的に整理するアプローチです。
戦略マップを使うことで、健康への投資がどのように企業価値向上に結びつくのかが明確になり、経営層への説明責任もバッチリ果たせます。
適切なKPI設定と継続的な見直し・改善が、健康経営の成果を最大化し、従業員の健康と企業の成長が両立する好循環を生み出す鍵となるんですよ。
「うちの会社の健康経営、もっと戦略的に進めたい!」
そう思ったら、まずはKPI設計から見直してみませんか?
健康経営でよく使われるKPI一覧:あなたの会社はどれを測る?
健康経営の成果を測るために、どんなKPIを使えばいいのか、気になりますよね。
ここでは、多くの企業で活用されている代表的なKPIをいくつかご紹介します。あなたの会社の健康課題に合わせて、ぴったりのKPIを見つけてみてくださいね!
① 離職率:健康経営は「辞めない会社」を作る!
「健康経営と離職率って関係あるの?」と思うかもしれませんが、実は大アリなんです!従業員が心身ともに健康で、働きやすい環境が整っている会社は、自然と「ここで長く働きたい」と思う人が増えるもの。
実際に、健康経営に力を入れた結果、離職率が30%以上改善したという企業や、離職率が14%まで低下し、定着率が90%に上昇したという嬉しいデータも報告されています。健康経営は、優秀な人材の流出を防ぎ、企業を強くする効果があるんですね。
② 健診受診率:まずは「知る」ことから始めよう!
従業員の健康状態を把握する上で、健康診断は基本中の基本。でも、「忙しくてなかなか行けない…」なんて声も聞きますよね。だからこそ、企業が積極的に受診を促し、受診率を上げることが重要なんです。
ある企業では、健康経営の重点テーマとして「がん対策」を掲げ、その結果、健診受診率が73.0%から87.1%に向上した事例があります。また、特定健診の受診率が75.0%から78.6%にアップしたケースも。受診率が上がれば、病気の早期発見・早期治療に繋がり、従業員の健康寿命を延ばすことにも貢献できます。
③ ストレスチェック結果:心の健康も「見える化」しよう!
現代社会において、メンタルヘルスは避けて通れない課題です。ストレスチェックは、従業員の心の健康状態を把握し、高ストレス者へのケアだけでなく、職場全体の環境改善にも役立つ重要なツール。
ストレスチェックの結果を分析することで、休業発生の未然防止や労働生産性の低下を防ぐ効果が期待できます。実際に、集団分析の結果から「部署内の改善すべき課題が明らかになった」り、「エンゲージメントの偏りが課題」として浮上し、具体的な改善策に繋がった事例も多数あります。心の健康も「見える化」して、働きやすい職場づくりを進めましょう!
健康経営KPI設定の3ステップ:あなたの会社に最適な指標を見つけよう!
「よし、KPIを設定しよう!」と思っても、どこから手をつけていいか迷いますよね。ご安心ください!ここでは、シンプルで分かりやすい3つのステップで、あなたの会社に最適なKPIを見つける方法をご紹介します。
【STEP1】目指す姿を表す重要指標を設定する
まずは、あなたの会社が健康経営を通じて「どんな未来を目指したいのか」を明確にすることから始めましょう。これは、健康経営で解決したい経営課題と、それに繋がる健康課題をハッキリさせる作業です。
- 経営層との対話: 社長や役員の方々と直接ディスカッションする機会があれば、ぜひ活用しましょう。経営層が健康経営に何を期待しているのか、どんな会社にしたいのか、その「想い」を言語化することが重要です。
- 経営理念・健康経営宣言の読み解き: もし直接話す機会が難しければ、自社のホームページに掲載されているトップメッセージや経営理念、健康経営宣言などをじっくり読み返してみましょう。そこに込められた「組織のありたい姿」を深く理解するヒントが隠されています。
- 言葉の定義を明確に: 例えば、「従業員がイキイキと健康に働ける会社」という健康宣言があったとします。この「イキイキと健康」とは具体的にどんな状態を指すのか?「労働生産性が今よりも高く、離職率が今よりもっと低く、従業員の満足度が今より高い状態」といったように、自社なりの定義を明確にしましょう。そして、それを自己評価するための指標(例:労働生産性、離職率、従業員満足度)を具体的に設定します。
ポイント: 経営理念や健康宣言が形骸化しないよう、言葉の定義を曖昧にせず、具体的な「目指す状態」を明らかにすることが、このステップの鍵ですよ。
【STEP2】目指す姿を実現するための中間指標を設定&打ち出す
目指す姿が明確になったら、次はその目標を達成するための中間指標、つまり具体的なKPIを設定していきます。ここで設定するのは、アウトカム指標、パフォーマンス指標、アウトプット指標といった、健康経営の具体的な成果を示す指標です。
- 経営層や従業員が関心を持つ指標にフォーカス: 設定したKPIを、担当者や事務局だけで抱え込んでしまうのはもったいない!経営層や従業員が「これなら自分ごととして捉えられる!」と感じるような、分かりやすく、関心を持ってもらいやすい指標に絞って社内アナウンスをしましょう。すべての指標を追いかけるのではなく、戦略的に重要な指標にフォーカスすることで、全社的な巻き込みを促進し、健康経営を前進させることができます。
【STEP3】データ収集・可視化でPDCAサイクルを回す
KPIを設定したら、次はそれを測るためのデータ収集と「見える化」が重要です。そして、その結果をもとに改善策を立て、実行し、また評価する…というPDCAサイクルを回していくことで、健康経営の効果を最大化できます。
健康経営の「見える化」を加速!データ収集・可視化のコツ

KPIを設定しただけでは、健康経営は前に進みません。大切なのは、そのKPIを測るためのデータをしっかり集めて、「見える化」すること。ここでは、健康経営のデータを効率的に収集し、分かりやすく可視化するための3つのステップをご紹介します。
ステップ1:まずは「あるデータ」を整理しよう!
「データ収集って難しそう…」と感じるかもしれませんが、実はあなたの会社には、すでにたくさんの健康関連データがあるはずです。まずは、それらを整理することから始めましょう。
主なデータ例
- 定期健康診断の結果: BMI、血圧、脂質などの数値は、従業員の身体的健康状態を把握する基本データです。
- ストレスチェックのスコア: 従業員のメンタルヘルス状態や、職場ごとのストレス傾向を把握できます。
- 欠勤・休職日数: 従業員の健康状態や心理的なストレスが、労働にどう影響しているかを示す重要な指標です。
- 社内アンケート結果: 睡眠・食事・運動習慣など、従業員のライフスタイルに関する貴重な情報が得られます。
【重要】個人情報の取り扱いには細心の注意を払いましょう。 個人を特定しない集計や部署単位での集計にすることで、従業員も安心して協力してくれますよ。目的は「支援」であることをしっかり伝えましょう。
ステップ2:集めたデータを「分析」して「可視化」しよう!
データを集めたら、次はそれを分析し、グラフやマップなどで「見える化」していきます。これにより、漠然としていた健康課題が、具体的な数字や傾向として浮かび上がってきます。
具体的な可視化例
- 健康診断の項目別平均値の推移グラフ: 年ごとの変化を見ることで、全社的な健康課題の傾向を把握できます。
- 部署ごとのストレス傾向マップ: どの部署でストレスが高い傾向にあるのか、視覚的に把握し、重点的なケアが必要な部署を特定できます。
- 欠勤率の月別推移と季節変動: 特定の時期に欠勤が増える傾向がないかなど、季節的な要因やイベントとの関連性を分析できます。
「専門的なツールがないと無理?」と思うかもしれませんが、GoogleスプレッドシートやBIツールなど、無料でも十分活用できるツールはたくさんあります。まずは手軽に始められるものから試してみるのがおすすめです。
ステップ3:可視化した結果を「改善施策」にフィードバック!
「見える化」の最終目的は、具体的な改善施策につなげること。データが示す課題に対して、ピンポイントで効果的な打ち手を講じましょう。
改善施策の例
- 「睡眠不足が多い」というデータが出たら… → 睡眠セミナーの開催や、快眠グッズの紹介など。
- 「運動習慣が少ない」というデータが出たら… → ウォーキングキャンペーンの実施や、社内フィットネスイベントの企画など。
- 「ストレス値が高い」というデータが出たら… → EAP(従業員支援プログラム)の導入、カウンセリング体制の強化、上司向けのメンタルヘルス研修など。
このように、データに基づいてPDCAサイクルを回すことで、健康経営の施策はどんどん洗練され、より大きな成果へと繋がっていくはずです。
KPIを活用した改善事例:健康経営で会社も従業員もハッピーに!
ここまで、KPI設計の重要性や設定方法、データ活用について見てきました。でも、「実際にKPIを活用して、どんな良いことがあったの?」と、具体的な事例が気になりますよね。ここでは、KPIを上手に活用して健康経営を成功させた事例をいくつかご紹介します。
事例1:離職率が大幅改善!働きがいのある職場へ
ある企業では、健康経営の取り組みを始める前、従業員の健康状態や職場環境への不満から、離職率が高いという課題を抱えていました。そこで、健康経営のKPIとして「離職率」を設定し、従業員の健康診断受診率向上、ストレスチェック後の職場環境改善、メンタルヘルス研修の実施など、様々な施策を展開しました。
結果として、健康経営推進後には離職率が30%以上改善し、従業員の定着率も大幅に向上。従業員からは「会社が私たちの健康を真剣に考えてくれていると感じる」「安心して長く働ける」といった声が聞かれるようになり、働きがいのある職場へと変貌を遂げました。健康経営が、人材定着の強力な武器になることを示す好事例ですね。
事例2:健診受診率アップで、従業員の健康意識が向上!
別の企業では、従業員の健康診断受診率が伸び悩んでおり、病気の早期発見・早期治療の機会を逃しているという課題がありました。そこで、KPIとして「健診受診率」を設定し、受診しやすい環境整備(社内での集団健診実施、受診時間の柔軟化など)や、健康診断の重要性を啓発する情報発信を強化しました。
その結果、健診受診率が73.0%から87.1%へと大きく向上。さらに、特定健診の受診率も75.0%から78.6%にアップしました。受診率向上だけでなく、従業員一人ひとりが自身の健康状態に関心を持つようになり、生活習慣の改善に取り組むきっかけにもなりました。健康経営は、従業員の健康意識を高める教育的な側面も持ち合わせているんですね。
事例3:ストレスチェック結果を活用し、心理的安全性の高い職場へ
ある大企業では、ストレスチェックの実施はしていたものの、その結果を十分に活用できていないという課題がありました。そこで、KPIとして「ストレスチェックにおける高ストレス者の割合」と「職場環境改善に関する従業員満足度」を設定。ストレスチェックの集団分析結果を詳細に分析し、高ストレス傾向にある部署に対して、産業医やカウンセラーによる個別面談の強化、管理職向けのラインケア研修、部署ごとのワークショップ開催などを行いました。
これらの取り組みにより、高ストレス者の割合は徐々に減少し、従業員アンケートでは「困った時に相談しやすい雰囲気になった」「心理的安全性が高まった」といったポジティブな回答が増加しました。ストレスチェックの結果を単なるデータで終わらせず、具体的なアクションに繋げることで、従業員が安心して働ける心理的安全性の高い職場環境を築くことに成功した事例です。
これらの事例からもわかるように、KPIを適切に設定し、その結果に基づいてPDCAサイクルを回すことで、健康経営は単なる福利厚生ではなく、企業の成長を加速させる戦略的な投資となるのです。
まとめ:健康経営の成果はKPIで「見える化」できる!
今回は、健康経営の成果を測るためのKPI設計と活用法について、たっぷりとお話ししてきました。いかがでしたでしょうか?
健康経営の成果を最大化するには、KPI(重要業績評価指標)による「見える化」が不可欠です。KPI設計は、まず「目指す姿」を明確にし、離職率、健診受診率、ストレスチェック結果などの具体的な指標を設定します。そして、データ収集・可視化を通じてPDCAサイクルを回し、改善施策に繋げることで、従業員の健康増進はもちろん、離職率の低下、生産性の向上、ひいては企業価値の向上へと繋がります。
「健康経営優良法人」の認定を目指す人事担当者の皆さん、そして、これから健康経営をさらに進化させたいと考えている皆さん。ぜひ、この記事でご紹介したKPI設計の考え方や活用法を参考に、あなたの会社の健康経営を次のステージへと進めてみてくださいね。きっと、会社も従業員も、もっとハッピーになる未来が待っていますよ!
FiNC for BUSINESSでは、健康経営を推進する企業様をサポートする様々なソリューションをご用意しています。ぜひお気軽にご相談ください。
✅ FiNC for BUSINESS のサービス資料はこちら
📢 無料相談・お問い合わせはこちら